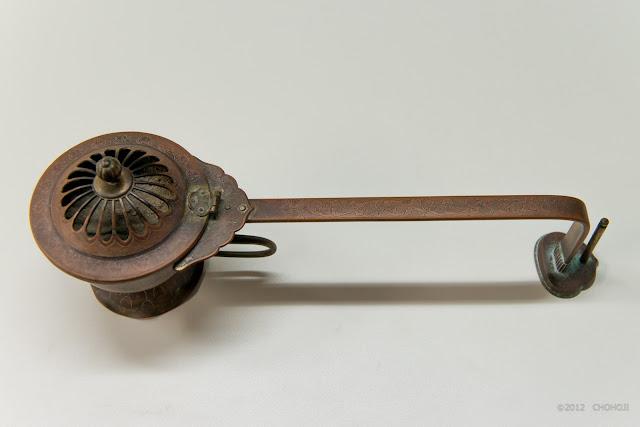紀州初代藩主南龍公が祈願を込めていた地蔵菩薩です
江戸時代には紀州藩主のご家族様だけが参拝することができた、長保寺客殿の奥まったところにある内仏堂に安置されています
長保寺には1000年の歴史がありますから、人目に触れないところにも奥深い歴史が秘められているのです
家族を社会の基本と考えていた紀州徳川家では、地蔵菩薩を子育ての仏として篤く信仰していました
過去帳を見ると、明治の初期までは、藩主だろうが庶民だろうが嬰児や幼児の死亡率は一緒です
七歳まで生き残るのは4~5人に一人くらいです
医薬の力に限界のある時代ですから、仏に頼る気持ちは、現代よりもずっと強かったでしょう