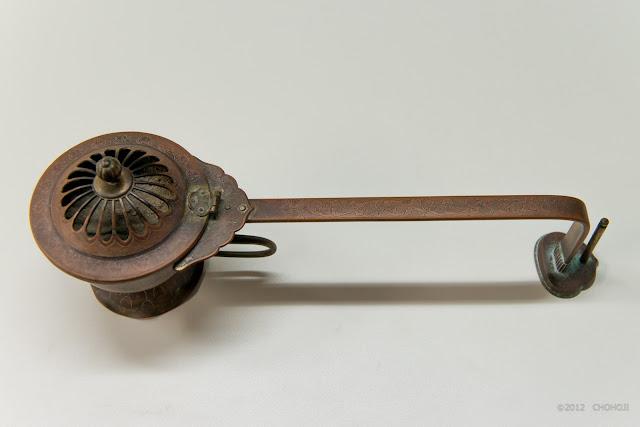和歌山県打田町の大西勝様に、本日ご寄贈いただきました
大西様は、骨董屋ですが、お寺に所縁のある画像ということで、ご寄贈いただけることになりました
深く感謝申し上げます
どうも長生きできてめでたいというような内容のようです
長保寺では、もともと堯謙の画像(下津町上字蔵)をお預かりしていて
絵の人相はだいぶ違うと言っていいでしょう
しかし、左下の落款は同じものですから、ご寄贈いただいた掛軸は本物ですね
溜池を開削して飢饉から人々を救ったことで、歴代住職の中でも特に慕われています
ここからは、浜中村史の記録です
堯謙とは長保寺住職第12世大僧都堯謙である。
宝暦3年(1763)播州明石に生まれ、幼少の頃、兵庫港の能福寺に入り出家、得度をした。
(今も神戸に子孫の井上さんというお家があります)
その後、比叡山に登り、修学、精励し、同山の遺教院の住職となった。学識深く、徳望高い人として尊敬を集めた。
文政6年(1823)長保寺へ移住し、地域の為に力を注いだ。
とりわけ、天保3年(1832)から8年には毎年のように干ばつ、降雨、暴風雨などによる凶作がうち続き大飢饉となった。
農民の生活は悲惨きわまりないものであった。
そこで堯謙は干ばつや飢饉にあえぐ農民を救うべく長保寺池の造営工事を起こした。農民を人夫として使役し、賃金を支払って生活を安定させ、また東光寺池も改削して、農民の苦境を救った。
(この飢饉で紀州では十人に一人が飢え死にしたと伝えられているが、上字では一人の死者も出さなかった)
天保11年(1840)退隠して阿耨院(あのくいん)と称した。
老年になり、般若心経八万四千巻を書写する願を立て、以来死に至るまで日夜書写に励み、これを広く人々に施したという。
ここ近在には堯謙の手になる般若心経がかなり多く残されている。
また長保寺池畔には天保13年9月(1842)堯謙が謹書した般若心経の石碑が建てられている。
弘化2年(1845)5月2日、82歳にて没す。毎年、命日の5月2日には、上地区の関係者が長保寺に集まり読経、供養、墓参をして堯謙の偉業を偲び、後世に伝えている。
(現在でも毎年続けられています)
願還生此界 為僧事覚王 斯意人莫訝 難忘故郷
願わくば此の界に生まれ還らん 僧の覚王につかえんがためなり その意を人いぶかしむことなかれ 忘れがたきはこれ故郷
死ぬるとき 面(おもて)は西に向かえども 心は娑婆に 有明の月
掛け軸は長保寺がお預かりしていますが、上字の所有です









-1-2.jpg)
.jpg)